| 山口市瑠璃光寺 ⇔ 三田尻茶屋町 その2 |
TOPに戻る 第1区分TOP 次のページ 第2区分TOP 前のページ |
|
   |
||
| 佐波山トンネル越えの入口立札 | 佐波山越えの萩往還 | 峠を超えて防府市街が見えてきました |
| ここが佐波山トンネル越えの入口です。 国道262号線はこの地点からトンネルに入りますが、萩往還は左の立札のところより右の山に入ります。右側の写真がトンネル越えの萩往還の一部です。この間は全てアスファルトで舗装されていますが、道幅は3m程度です。この付近の地図はこちらで確認してください。現在の行政区分ではこの峠が山口市と防府市の境となります。山口市の瑠璃光寺の出発点より14.15kmの距離になります。終点の三田尻御茶屋町までは8.86kmです。 最後の登りだ 佐波山トンネルのある峠を越えると下の左の写真の道路に出てきます。写真の右側の道路は国道262号線で峠の下をトンネルで貫通しています。余談ですが、この国道は2004年末に「イチロー道路」と名づけられました。(大リーグの最多ヒット数262本をイチローが達成したことを記念して) 防府市内が見えたぞ 峠を越えて、下りて来たところで、視界が開け、遠く向島や防府市内が見えてきました。やっと、終点近くになりました。この景色を見ると、急に元気が出てきました。 |
||
 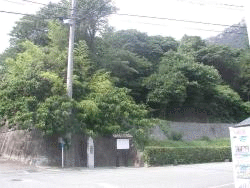  |
||
| 佐波山越えの萩往還と国道262号 | 砲台跡 | 剣神社 |
| 砲台跡地の側を左折し右田市に こんもりとした森が勝坂砲台の跡地です。萩往還はこの角を曲がり、右田市に入ります。右田市について立札には 「右田市は、昔から商業が盛んで、江戸時代は「家数45軒」といわれ当時としてはかなりの集落でした。この道を下った十字路はかっては三叉路で、石州街道との分岐点でした。この萩往還は、明治時代中頃まで主要な道路として利用されていました。」 と記載されていました。 剣神社 山陽新幹線のガードを潜る右手に剣神社があります。そこを南下し、佐波川まで直線的に道は続きます。剣神社内にはこの近くに流れている川にかかる石橋が移設されています。 佐波川を昔は「渡し」、で今は「橋で」 昔は佐波川は舟で渡っておりましたが、今は橋が出来ております。今の佐波川と昔のそれとは、川の大きさ、景観は違うでしょうが、写真のような風景を見ながら川を渡ったことでしょう。 佐波川は昔から物資の輸送経路として重要な役目を果たしてきました。この川の上流にある徳地町から材木を運び、奈良の東大寺の柱の材料に使用したそうです。橋を渡って、そのまま道路を直進してはいけません。下の地図で 赤く塗っているところが萩往還です。橋を直進しても何れは萩往還と合流しますが、そこは萩往還ではありません。大通りと合流した地点から暫く南下したところで、左側に入ります。その交差点のところに萩往還標識が立っています。立札には次のようなことが記載されています。 |
||
 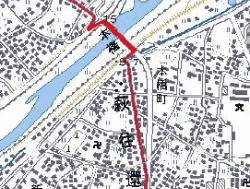  |
||
| 佐波川(上流を見る) | 佐波川付近の萩往還地図 | 山陽道と萩往還の分岐点 |
 |
萩往還と山陽道の交差点 萩往還は,江戸時代のはじめ萩城と毛利氏の水軍本拠地である御舟倉(防府市三田尻)を結ぶ,参勤交代の道として整備された街道です。しかし、中国山地をこえるこのルートには、険しい坂や峠が多く、道行き人たちにとっては苦労の多い旅であったと思われます。 佐波川左岸の「船本」からここまでは、「山口小路」と言われ道の両側には往還松が植えられていました。この地点は、萩往還と山陽道が分かれる処で,かってはT字路でした。東に折れると、今市・新町・中市・前小路と続き、中世から鳥居前町として商業が発達した宮市になります。萩往還は天満宮前まで山陽道と重複しています。 左の地図で黄緑色は山陽道で、交差点が分岐点です。 |
|
| TOPに戻る 次のページ 前のページ ページの先頭 第1区分TOP 第2区分TOP | ||